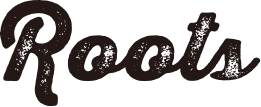今回の参議院選挙、メディアやSNS、Youtubeを
ザッピングしながら見ておりますが、
まぁいろんな意味で盛り上がっていますね・・・
既に期日前投票を済ませておりますが、
いずれにしても日本の、子供達の未来が明るくなる
地域社会を目指していきたいものです。
この1週間はホームステイを受けれつつ、
複数のオンラインMTG、調査の集計、そして来週からの
対馬出張の打合せ・ヒアリングのアポイントを。
私たちの仕事の半分は段取り、先方やブレインとの
アポイント・調整と言っても過言ではありません。
お客さんからのオーダーの本質をきちんと理解するか。
貴重な出張をいかに有意義にするか。
先方や関係者との対話からいかに真意を引き出すか。
外部のブレインが事業の意図を理解し、その地域のために
持つべきスキルをいかに全力投球してくれるか。
これらの積み重ねが、良い結果を生み出してくれるのです。
来週からの出張の段取りはなかなかに手強い調整でした(笑)
この段取りが良い結果を生み出すよう、あとは体調を
整えて現場に繰り出すのみです。