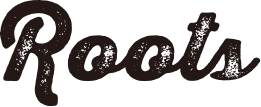一昨日に対馬の観光関係者と出来立てほやほやのおいづるを着て、
対馬六観音まいりの巡拝へ。
大尊敬する大西住職が各所で御祈祷をしていただき、
みんなで観音様にお祈りしました。
観音様が顕現する相応しい場所ってあるんですって。
佐護観音は近くに川が流れ、伸びやかな風景が広がり、
とても好きな場所ですね。





一見観光と信仰って関係ないかもしれませんが、
昔は「巡礼」を通して地域の交流をしたり、旅に出たりしていた
ことを考えると、「巡礼」が観光のスタンダードだったと言える
かもしれません。
3年前に対馬の住職さんと出会い、信仰のことに興味を持ち始めて、
対馬の文化である「対馬六観音」や「地蔵盆」のことを調べて
リーフレットを作り、いろんな本を読んだり、対馬で開催される
仏教体験や節分祭、仏教文化講座に参加することで、
今の日本にこそ「信仰」が必要なのではないかと思います。
一般的に「宗教」って胡散臭くみられがちですが、
「宗教」って言葉自体も実は江戸とか明治の時代に作られたもので、
イスラム教とかキリスト教とかの台頭で自分達の教えを普及し、守る
ための言葉。「信仰」は「宗教」って言葉が生まれる前からずっと
日本に根付いてきた考えであり、生きる知恵だったのです。
厳しい自然の中で、自然と共生して行くために山や海の神様を祀り。
自分達の生活の食糧を得るために、五穀豊穣を願い。
自分達の政ごとがうまく行くように、観音様にお祈りをしたり。
暮らしのあちこちにその文化が息づいていたんですね。
日本人のその精神が、今では海外に人たちに評価されており、
対馬にも禅の修行や巡礼をする人達が増えてきています。
祈りの文化。自然と共生する優しさ。
自分達の立ち位置・先行きを失いかけている日本にこそ、
「信仰」の文化が必要なんだと思うんです。
その精神文化こそが、日本人の誇りであり美しさだと。
ダラダラと書きましたが、そんな日本の美しさが
日本の果ての対馬にはまだ残っています。
是非とも対馬に来て、六観音を参って、
感じて、考えて欲しいです。
私の大好きな住職さんが伝えてくれています。