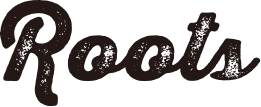先週弾丸でベトナムに行ってきました。
今回訪ねたのは、ニャチャンというリゾート地。
日本ではあまり知られていない観光地ですが、
世界中から癒しを求めてやってくるビーチリゾートです。


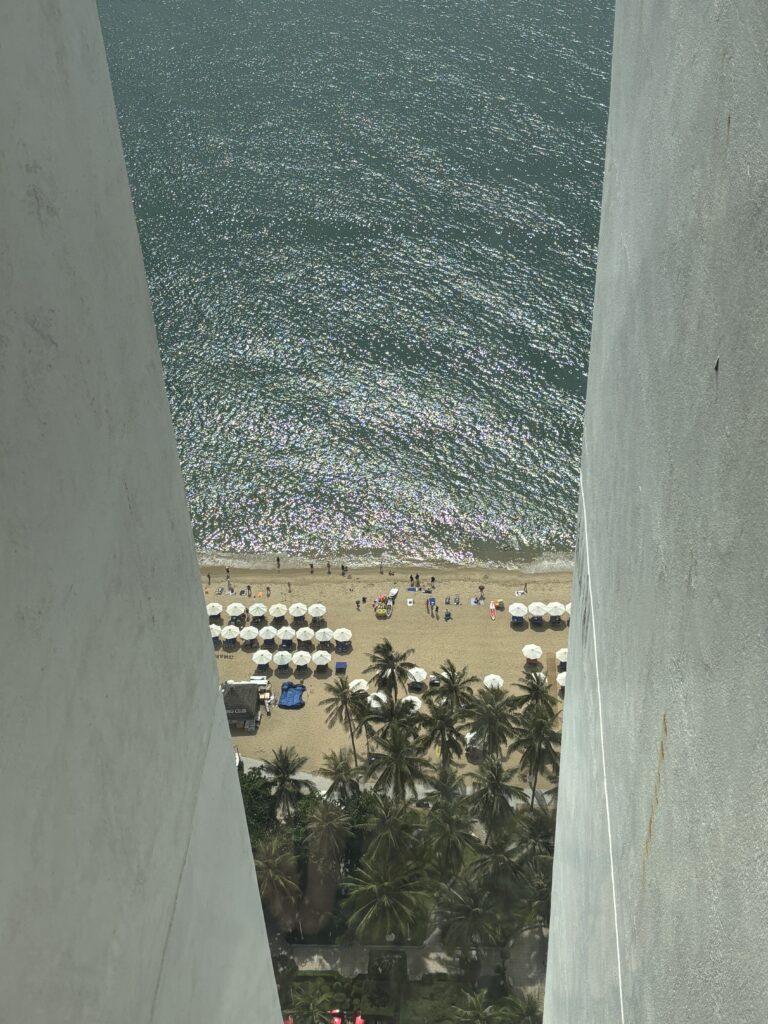

宿泊したホテルの前には約7kmずーっとビーチが広がっていて、
早朝の4、5時から海水浴に入り、深夜は大容量の音楽がガンガン流れ、
眠らないビーチリゾート地です。
まぁでも人だらけ。観光客も観光地を巡るっていうよりは
ホテルとビーチの往復している人ばかりで、のーんびり過ごしている感じ。
観光客だけでなく、地元の人達の癒やしの場所になっていました。
初日に地元ガイドをお願いして観光地巡り。
ダム市場でお買い物したり、海の中に浮かぶ自然記念物、お寺とか。
まぁとにかく暑かったですね。
ベトナムはご飯が本当に美味しくて、野菜もしっかりとれる。
すっかりフォーの虜になりました。




上記が街中のアーバンビーチリゾートで、旅の後半は島に渡って
アイランドビーチリゾートを満喫しに。


前半に宿泊したホテルの事業者が同じく経営しているようで、
島全体がリゾート会社のものって感じでした。
まぁちょっと日本では考えられませんね・・・
こちらのリゾートはプライベート感満載で、ビーチも人がおらず、
敷地内のプールもレストランもコテージも、
ゆーったりと過ごせる作りになっています。
それでも金額的には日本の1/3くらいの金額ですね。
ご飯も美味しいし安いし、それは世界中から観光客が来ますね。
宿泊客はアジアというよりは欧米系・ロシア系の観光客が多かった。
同じ島の中に泥風呂があると聞いて、島の反対側のリゾート地に行きましたが、
もうそこは中国人だらけで完全なるオーバーツーリズムでした。。。

どうやら本土からの日帰りツアーで来ているようですね。
ここはリゾート地なのか?と疑ってしまうような人混みで、
ゆっくりしに来たはずなのにどっと疲れてしまいました・・・
人に来てもらうことは決して悪いことではないけど、
でもやはりそのリゾート地に求める価値は自然であり、
ゆっくりした時間だと思います。
その自然資本を守っていくためには、適切なキャパがあり、
そのためにはきちんとルールや金額設定を作っていく必要が
あるのではないでしょうか。
日本も人ごとではありません。
日本食や伝統文化、自然、建物は世界に誇れるものがあり、
円安が追い打ちをかけて、今後もっとインバウンドは増えていくでしょう。
その中でどう舵を切っていくのか?
経済至上主義に邁進すると大変なことになるでしょう。
日本人の生活は脅かされ、観光に携わる事業者と市民での軋轢が
生まれ、いつしか大切な資源は消費されるだけになってしまいます。
日本の価値を未来に継承していく・保全していくことを前提として、
どうやって観光と生活のバランスを保ち、経済循環をしていくのか
仕組みを作っていくことが求められてきます。
そうならないうちに、今のうちからルール作りが必要です。
日本では知られていないベトナムのオーバーツーリズムの最前線で、
その必要性を痛感してきました。