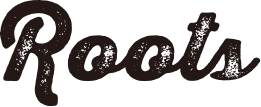プラハ・ウィーン旅備忘録4/自国の文化を味わえるコンテンツは作るもの!?
2025.05.26 / trip
ガイドツアーと重複するところはありますが、
その土地の文化を味わう体験こそが「旅の本丸」。
プラハとウィーンを旅する中で特に印象的だったことをご紹介します。
❶建築・街並み
プラハとウィーンは建築の宝庫。
プラハはガイドツアーに参加したクレメンティヌム図書館や、市民会館、
ストラホフ修道院と、圧倒的な美を誇る伝統的な建築物がそこかしこに。
また、キュビズム建築やフランクゲイリーの作品など、現代的な建築物が
あるのもまた面白い。伝統をベースとしながらも、現代を取り入れる。
それがまた街としての層を厚くするんでしょうねー。
プラハが芸術的な繊細な街だとすると、ウィーンはハプスブルグ家の
豪華で広大な街というイメージ。2つを見比べるととても面白い。
ウィーンのメインは、ハプスブルグ家のとんでもない規模感の
王宮だったり庭園だったりが観光名所となっています。
もちろんそちらもお上りさんで行きましたが、ハプスブルグ家の
歴史が何よりも面白い。本で読んだり、映画で見たり、プラハのガイド
の佐藤さんから色々と学んでインプットしましたが、そちらの説明は
様々ネットでも情報が出ているのでそちらをご参照ください。
ウィーンの建築で特に面白かったのが、ウィーンを代表する近代建築家で
あるフンデルトヴァッサーの建築群。実は日本でもいくつか建築を手がけて
いますが、これだけまとまってみれるのはウィーンならでは。
奇想天外な建築を手がける彼ですが、実は日本文化に対する愛情が深く、
浮世絵や版画に影響を受けているのが印象的です。
そしてもう1つ。オーストリアを代表するデザイナーのヨーゼフホフマン
をはじめ、オーストラリア発祥の家具やデザインを体系的に俯瞰できたのは
とてもよかったです!
まだまだ書ききれないことばかりですが、この辺で。








❷アート
プラハのミュシャ、ウィーンのクリムト・エゴンシーレ。
各国を代表するアーティストの作品をゆっくり鑑賞することも
また旅の目的でした。
まずはミュシャ。プラハの中心部にあるミュシャ美術館は、
彼が手がけた広告ポスターを始め、生涯の作品を多数展示しています。
また、プラハ城や市民会館をはじめとして、ステンドグラスや天井画など
プラハを代表する建築物の中で楽しめるのもまた楽しい。
ですが、今回の旅で何よりも楽しみに、周到に計画をしたのが、
ブルノの郊外にあるモランスキー・クルムロフ城に展示している
「スラブ叙事詩」を見ること。このスラブ叙事詩は東京でも展示されて
長蛇の列だったみたいですが、なんと私達が行った日の朝一は貸切!!!
1作品の前で20分か30分くらいジーっくりと贅沢に鑑賞することが
できました。ほんとわざわざ行く価値があります。

ウィーンでは、クリムト、エゴンシーレ、ブリューゲル、ベラスケスなどの作品を
見る為に、分離派会館、美術史博物館、レオポルトミュージアムなどなどあちこち巡回。
分離派会館のクリムトの展示、レオポルトミュージアムのエゴンシーレ、よかったなー。
観に行く方のために写真は控えておきます。
あと、ウィーンに限らず、海外の美術館ではよく見かける光景ですが、
フンデルトヴァッサーのクンストハウスでは、地元の子どもたちが先輩アーティストの
作品を学びにきていました。こういう光景を見ることも、その国・その土地の文化力を
感じられて、とても満足度が上がります。

❸音楽
プラハ、ウィーンといえば、芸術の街。
クラシカルな伝統的なホールで、さらっとおしゃれして、
仕事帰りに音楽鑑賞することが地元の生活の楽しみ方。
せっかく行くなら是非とも味わいたい!と、
普段なら持って行かないジャケット・パンツ・革靴・ネクタイを持参して
地元のコンサートへ。
プラハのクレメンティヌムコンサート、ウィーンではウィーン少年合唱団、
楽友協会でのロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団のコンサートと
3回行きましたが、あの圧倒的な建築美と音響に包まれて、
それはそれは最高の時間でした。
やっぱり本場ですもんね、クオリティがすごいです。
そりゃー叶いませんよ。。。
日本で言うならば、雅楽や能狂言とかでしょうか。
神社とか能舞台で音楽のひとときを提供してはどうでしょうか。


❹食
どの国に旅する上でも「万国共通の文化体験」と言えるのが、
その土地の食文化を楽しむことではないでしょうか。
食べる楽しみがないところには自ずと足が向かないのでは?
プラハもウィーンも内陸なので、基本的にはお肉中心。
その土地の郷土料理やその料理が食べられる飲食店をネットや
google mapで調べて尋ねました。
海に面していない分、お魚料理はちょっと乏しい印象ですが、
その分味付けに創意工夫していろんなお肉の郷土料理がありますね。
そのお肉料理を引き立てるのがやはりチェコビール!
チェコはビールの消費量が世界一と言われるほどのビール党。
ガイドの佐藤さんがお話ししてましたが、チェコ人はほとんど食べずに、
つまみだけでひたすらビールを飲んでいると言ってましたが、
まさにそうでした。
ほとんどの飲食店では「ピルスナーウルケル」というチェコを代表する
ビールを推していて、他国のビールはほとんど扱っていない。
また、ビールに限らず、チェコのワインは自国で消費されるため
外に出回らないと言われており、お土産に買って帰りました。
自国のものを大切にする、自国のものを消費する。
当たり前のことなんですが、それが国民に浸透しているから素晴らしい。
気がつけば海外の飲食店が進出して、煽られ、西洋の食文化をとりいれ、
日本の食料自給率は深刻な状況で、減反政策のせいでお米は信じられない
くらいに爆上がりして(涙)
自国や地域の食文化を大切にすることこそが、結果的に観光客を
惹きつけ、責任持って行動してくれる観光へと繋がっていくはずなんですが。。。




❺蚤の市
国内でもよく行きますが、海外の旅先で蚤の市を探して出かけるのも
楽しみの1つ。基本蚤の市は週に1回(土日とか休みの開催が多い)
なので、最初に蚤の市の日程を調べてからスケジューリングします。
プラハのクレメンティヌムの蚤の市は、それに合わせて
工程を組んだものの、どこに行っても見つからず、現地の人に聞いたら、
「もうとっくの昔になくなったよ」って。。。
ガイドブック、更新してください(涙)
で、リベンジのために、ウィーンのナッシュマルクト蚤の市へ。
こちらはかなり規模が大きく期待してましたが、まさかの雨(涙)

出店数は限られていましたが、それでも掘り出し物がありました!
1年前に無くしてしまったシルバーアクセサリーやインテリアになる
置き物を探して端から端まで見てまわりました。
その中で、センスの良いアンティーク商品を扱うお店でわいわい言いながら
物色していたら、日本語で話しかけてくる女性が。お話を聞くと、国内のお店で
扱うアンティーク商品の買い付けに来ているのだとか。
この蚤の市には定期的に来ているようで、「ここのお店は間違いないよ!」と
太鼓判を押してもらったので、お店のお店のオーナーさんと色々交渉して購入。
蚤の市は掘り出し物の発見はもちろんのこと、こういう出会いがあって
楽しいんです。やめられません。
さて、最初の問いにあるように、
「自国の文化を味わえるコンテンツは新たに作るものか」どうか。
建築も芸術も食も、基本的にはその土地にずっと根ざして、市民が大切に
育んできたものであり、何か新たに作ったコンテンツではありません。
国内で見られるようなコスプレ的な衣装纏ったり、地元の食材を活用した
料理開発をしたり、インスタ映えするようなスポットを作ったり、
いわば流行りと一過性に便乗したコンテンツはそこにはありません。
「別に何もしませんけど、自国の文化を味わいたければどうぞ!」
って、お客さんに合わせるのではなく、わざわざニーズに対して
お金をかけるものではないんですね。
その土地の光を観に行くのはあくまで旅人ですから。
海外の人から言うと、フンデルトヴァッサーのように、
やはり日本独自の、地域独自の文化を味わいたいって思いませんかね?
それは幾多の時代に花咲いた芸術であり、歴史物語であり、日本食であり。
日本の信仰文化体験や登山、ものづくりや農業漁業といった産業も。
ただ、もともとよその人たちがみたり体験したり想定されていないものも
あるでしょうから、そこに「接点」を作ることがコンテンツ作りに
必要なんじゃないかと思うんです。
それ自体に手を加えたり、意味を変えることはダメで、
伝え方や関わり方、参加方法の手段を変えること。
対馬の浅茅湾のシーカヤックとかはまさに好例ですね。
かつて遣隋使達が渡った大陸へのルートや人工物1つない自然、
防人達が日本を守るために築いた金田城の歴史物語を
「シーカヤック」という手段を通して体感する。
世界の人達にも絶賛される素晴らしいコンテンツだと思っています。
まだまだ書ききれないことがたくさんありますが、
キリがないのでこの辺で。
また旅に出る日を楽しみに。